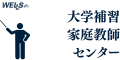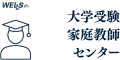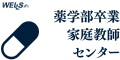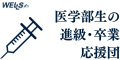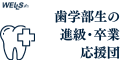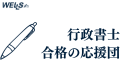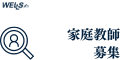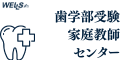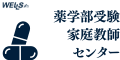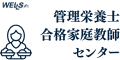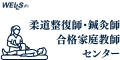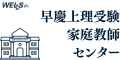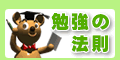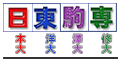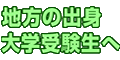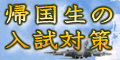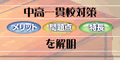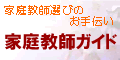薬学部「再試験」を乗り越えるための鉄壁対策ガイド|留年を回避する最後の砦
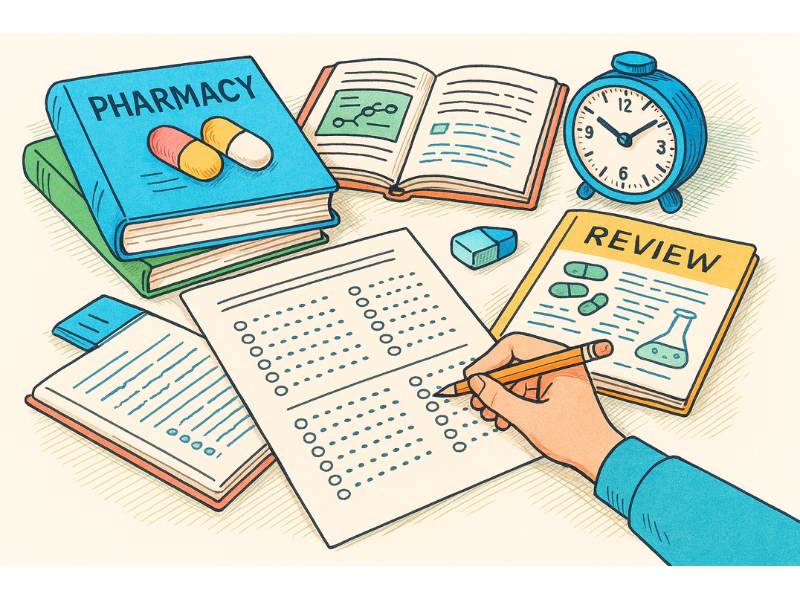
この記事では、定期試験で不可となり再試験を控えた薬学部生へ向けて、短期間で合格率を上げるための戦略と実践的な勉強法をわかりやすく整理します。限られた時間を最大限に活用して、再試験を確実に突破しましょう。
はじめに
- 試験結果を待たず、できるだけ早く再試験対策を始める。
- 本試験の「何がまずかったか」を1問ずつ分析し、原因に応じた対策を立てる。
- 本試験の問題を「満点を取れるまで」徹底的に解き直す。
- 教授・先輩・専門家の力は遠慮なく借りる。
再試験対策の基本方針:即行動・原因特定・重点攻略
再試験で勝つための三本柱は「すぐ始める」「原因を明確にする」「出題傾向に沿って重点を固める」です。特に、手応えが薄かった科目は合否を待たずに再対策を始めてください。時間が最大の制約です。
本試験の振り返り(必須の3ステップ)
- 出題傾向を把握する
どの範囲から、どの形式で出題されたかを確認します。計算問題が多かったか、理論重視だったかなどを整理すると、再試験で狙われやすい箇所が見えてきます。 - 敗因を分類する
各誤答について「ケアレスミス」「知識不足」「時間配分の失敗」「応用力不足」など原因を明確にします。原因別に対策を分けることで、短期で効果が出ます。 - 授業で強調されていた箇所を確認する
教授が講義や小テストで繰り返していたポイントは再出題の可能性が高いです。講義ノートや教材に戻り、強調箇所を再確認しましょう。
実践プラン:再試験直前にやるべきこと(段取り)
ステップ1:本試験の問題を「何も見ずに」解き直す
本試験の問題を完全に再現し、解答を見ずに満点が取れるまで繰り返します。丸暗記で終わらせず、間違えた箇所は教科書やノートに戻り「なぜその答えか」を自分の言葉で説明できるようにしてください。
ステップ2:重点分野の周辺知識も固める
本試験で出た分野は、周辺知識も含めて出題されることが多いです。該当範囲の教科書を再読し、関連する短問を追加で解いておきます。
ステップ3:時間配分と解答手順を訓練する
時間不足が原因だった場合は、実際の試験時間を想定して模擬演習を行い、解答順序と時間配分を最適化します。計算問題は過程を簡潔に書く練習をして、時間短縮を図りましょう。
ステップ4:情報収集と共有を行う
同じ科目の再試験を受ける友人や先輩と情報交換して、出題傾向や有効だった対策を共有します。過去の再試験経験者の体験談は実践的なヒントになります。
効果的な学習テクニック(短期で効く)
- 間違いノートを作る:誤答番号・間違えた理由・正答の根拠を一行でまとめ、通勤・休憩時間に見返す。
- 「教えるつもり」で説明する」:自分で説明できるまで整理すると短期間で定着します。
- 計算問題は単位チェックを習慣化:単位ミスを減らせば得点伸長が早い。
- ショートブレイクを挟む:集中力が続かないときは短時間(5–10分)の休憩を挟む。
人の力を借りるタイミングと方法
- 教授への質問:分からない論点は早めに質問。講義の意図や重要ポイントを確認できます。
- 先輩・同期との勉強会:互いに問題を出し合い、弱点を補い合う。
- 家庭教師・個別指導:科目数が多い、または根本的に理解が追いつかない場合は専門家への依頼が効率的です。指導を依頼する際は「直近の本試験問題」を持参すると効果が高まります。
メンタル面の対処(短期集中でも大切)
再試験は短期間で結果を出すプレッシャーが強いですが、基本的な生活リズム(睡眠・食事)を崩すと効率が落ちます。深呼吸や短い散歩などで気分を切り替え、追い込み期でもセルフケアを忘れないでください。
最後に(行動リスト)
- 本試験の問題を今すぐコピーして、自力で1回解いてみる。
- 誤答を「原因別」に分類し、優先順位をつける。
- 明日の学習計画を「時間割形式」で作成する(何時に何を何分やるか)。
- 教授か先輩に質問するポイントを3つ整理しておく。
再試験は厳しいですが、戦略を立てて短期集中で取り組めば必ず結果は変わります。必要であれば、当センターのプロ家庭教師による再試験直前対策(短期集中)をご案内します。まずは状況をお知らせください。
参考文献(名前とURL)
- PASS MED. (2024). 薬学部の再試験の対策方法とは?ヒントは本試験にあり. https://passmed.co.jp/pharmacy/archives/143
- 薬学部家庭教師センター 帝京大学薬学部生必見!再試験を乗り越え、ストレート卒業を! https://pharmacy-m.info/info-10/
- ファルマスタッフ. (2021). 【薬学部向け】再試験・追試験への対策とは?留年しないためのポイント. https://www.38-8931.com/pharma-labo/yakugaku_topics/article/saishi-tsuishi.php