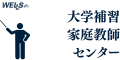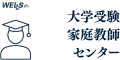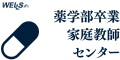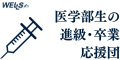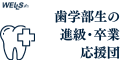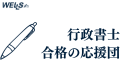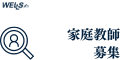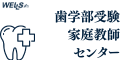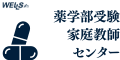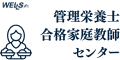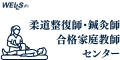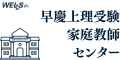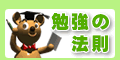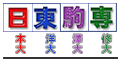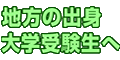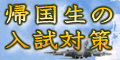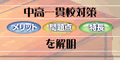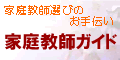薬学部5年生最大のイベント「実務実習」を乗り越え、飛躍するための心構えと対策

結論:
実務実習は「学びに行く」場です。謙虚に学ぶ姿勢と、毎日の小さな目標・振り返りを習慣化すれば、22週間で確実に成長できます。準備と心構えがあると、不安は自信に変わります。参照:文部科学省ガイドライン。
(参照:文部科学省「薬学実務実習に関するガイドライン」 https://www.mext.go.jp/content/20221226-mxt_igaku-1411266_00003_17.pdf)
実務実習とは(短く)
5年生の長期実務実習は、病院・薬局で合計22週間(各施設11週が原則)行われ、座学で得た知識を臨床で実践的に応用する期間です。詳しくは文部科学省の指針をご確認ください。
→ https://www.mext.go.jp/content/20221226-mxt_igaku-1411266_00003_17.pdf
基本の心構え(現場で評価されること)
- 「学ばせていただく」姿勢を忘れない:完璧さよりも、分からないことを素直に認め、率直に質問する姿勢が評価されます。参考:日本薬剤師会の実務実習関連資料。
→ https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/training - 安全第一:無資格で業務を行わないこと。実習での行為や手順には法的・倫理的な制約があるため、必ず指導薬剤師の指示に従ってください。参考:厚生労働省の臨床実務実習ガイドライン。
→ https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001203059.pdf - 記録と振り返り:日誌や週次振り返りの習慣をつけると学びが定着します(大学の実習管理マニュアルに従って記録)。大学ごとの運用例も参照してください(例:大学カリキュラム説明)。
→ 例:京都薬科大学カリキュラム紹介。https://www.kyoto-phu.ac.jp/education_research/curriculum_03
実習を成功に導く「3つのアクション」
毎日できる具体的な行動を、簡潔にまとめます。
1)毎日の小さな目標を立てる
「今日は処方監査の流れを一通り見る」「患者説明を1回やってみる」など、達成可能な小さな目標を1つ決めると学びが濃くなります。終わりに短く振り返りをして、日誌に記録しましょう。
(実務実習ガイドラインに「準備と振り返り」を促す記載あり)→ https://www.mext.go.jp/content/20221226-mxt_igaku-1411266_00003_17.pdf
2)質問は“自分で調べた証拠”を添えて行う
尋ねる前に自分で調べた事実や考えを一言添えると、教える側に「学ぶ熱意」が伝わり、より深い指導が受けられます。実務現場の教育で推奨される方法です。参考資料一覧→ https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/training
3)多職種と関わる機会を大切にする
薬剤師以外(看護師・医師・事務など)との連携が学びの源です。挨拶や感謝を忘れず、観察して学ぶ姿勢を示しましょう。チーム医療に関する概説資料も参考にしてください。
実習と国家試験(国試)勉強の両立法
- 実習中は「現場優先」:平日は実習・日誌・課題で手一杯になりがちです。無理に国試の長時間学習を詰め込むより、現場での「疑問→短時間復習」を習慣化する方が効果的です。実習前後の時間配分ガイドライン参照。
→ https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001203059.pdf - 現場学びを国試につなげる:その日の症例や薬剤について「なぜこの薬か」「副作用は?」と短時間で復習する習慣が、国試学習にも直結します(文献・教育ガイドラインに推奨例あり)。
→ https://www.mext.go.jp/content/20221226-mxt_igaku-1411266_00003_17.pdf - 週末・休暇を計画的に使う:週末や実習の合間にまとまった学習時間を確保する「メリハリ」が有効です。
実践的なテクニック(日常で使える)
- 日誌テンプレ:今日の目標/学んだこと3点/次に直すポイント1点。短く書く習慣が効果的(例:大学の実習管理例に準拠)。
- チェックリストを持つ:投薬指導の基本項目(目的、用法、注意点、副作用確認等)をメモ化しておくと安心。日本薬剤師会の資料も参照可能です。→ https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/training
- 録画での自己評価:患者説明や面談を録画(許可が得られる場合)して振り返ると、改善が早いです。シミュレーション教育の効果については日本語レビューがまとまっています。→ https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/56/3/56_161/_pdf/-char/ja/
よくある不安と短い答え(Q&A風)
- 教えてもらえないのでは?
-
指導薬剤師は教育担当です。学ぶ姿勢を示せば指導は受けられます(業界資料参照)。→ https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/training
- 日誌が大変で時間がない。
-
短くても毎日振り返る習慣が大事。テンプレ化して効率化しましょう(大学の実習管理例参照)。→ https://www.kyoto-phu.ac.jp/education_research/curriculum_03
- 失敗したらどうしよう?
-
失敗は学びの源。隠さず共有し、次に活かす姿勢が重要です(安全・臨床教育の観点)。→ https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001203059.pdf
ひとこと
当センターの家庭教師は、実務実習を乗り越えた多くの先輩学生をサポートしてきました。日誌の書き方のコツ、処方監査の実地練習、投薬指導のロールプレイなど、実習で役立つポイントを短期で補助できます。
さいごに
実務実習は期待と不安が交錯する時間です。小さな目標を積み重ね、学ぶ姿勢を保てば、22週間の経験は大きな力になります。体調管理を忘れず、毎日少しずつ前に進んでください。参照:文部科学省ガイドライン。→ https://www.mext.go.jp/content/20221226-mxt_igaku-1411266_00003_17.pdf
参考
- 文部科学省:「薬学実務実習に関するガイドライン(運用)」 — https://www.mext.go.jp/content/20221226-mxt_igaku-1411266_00003_17.pdf
- 文部科学省:「薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)」 — https://www.mext.go.jp/content/20230227-mxt_igaku-100000058_01.pdf
- 厚生労働省:臨床における実務実習に関するガイドライン(安全・運用) — https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001203059.pdf
- 日本薬剤師会:実務実習・教育資料一覧 — https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/training
- 学内運用例(参考):京都薬科大学 カリキュラム紹介 — https://www.kyoto-phu.ac.jp/education_research/curriculum_03
- シミュレーション教育レビュー(日本語・J-STAGE) — https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/56/3/56_161/_pdf/-char/ja/