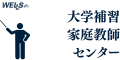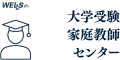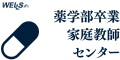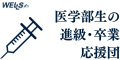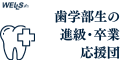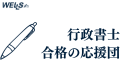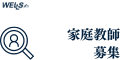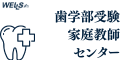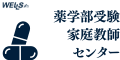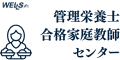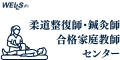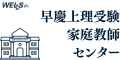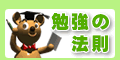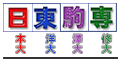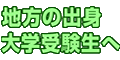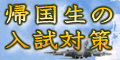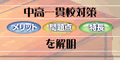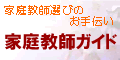薬学部2年生の壁「有機化学」は暗記じゃない!電子の気持ちを理解して得意科目に変える方法
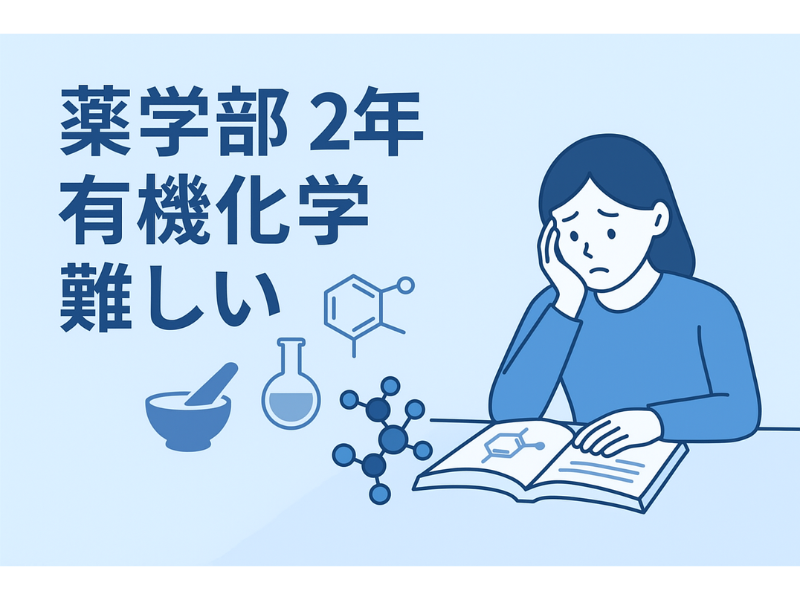
結論:
有機化学は「覚える科目」ではなく「考える科目」です。反応を丸暗記するのではなく、電子の動き(=巻き矢印)の原理を理解すれば、反応はパターンとして見えてきます。そうすると、新しい反応も「既に知っている型」の応用として読み解けるようになります。この記事では、2年生でつまずきがちな理由をエビデンスと共に示し、短期間で効率よく理解を深める具体的な勉強法をお伝えします。厚生労働省
まず、なぜ2年生の有機化学でつまずくのか?(ざっくり解説)
多くの学生が「突然難しくなった」と感じるのは次の理由からです。
- 学習の重心が“名前・構造”→“反応機構”に移る
1年で扱った内容(命名・構造)は「覚える部分」が多めですが、2年では「分子がどう変わるか=機構」を論理的に説明する力が必要になります。厚生労働省 - 高校範囲の「穴」が前提になっている
モル計算や電子の扱い(酸・塩基の考え方、極性など)があいまいだと、反応の“流れ”を追えません。まず土台が必要です。文部科学省 - 暗記中心の勉強法が通用しない
反応は数え切れないほどあり、丸暗記は非効率。教育研究では、能動的に「考えさせる」学習法が理解を深めると示されています。具体的には、反応の「なぜ」を説明させる授業や演習が有効です。azaleaenglish.com
有機化学を「理解」するための3つのステップ(実践的)
下の3ステップを繰り返すだけで、反応が“わかる”に変わります。
Step 1 — 「電子の気持ち」をつかむ(基礎観)
考え方: 電子は「負(−)っぽいところ」から「正(+)っぽいところ」へ動く。
まずは、分子の中でどこが電子を寄せやすいか(求核部位)、どこが引き寄せられやすいか(求電子部位)を見分ける練習をしましょう。
具体アクション: 教科書やノートの分子に色を塗る(電子が多いところを青、少ないところを赤)→素早く識別できるように反復。sy.rikkyo.ac.jp
Step 2 — 「巻き矢印」のルールを自分の手で書く(手を動かす)
考え方: 巻き矢印は“電子の流れ”を表す記号。
具体アクション: 参考書の反応をただ眺めるのではなく、自分の手で最初から最後まで巻き矢印を書き写す。矢印は「電子が出る場所」→「電子が入る場所」。間違えやすい典型パターン(求核付加、脱離、求電子置換など)を10回ずつ書きましょう。教育実践でも「手を動かす学習」が理解促進に効果的とされています。azaleaenglish.com
Step 3 — 代表反応を“型”で覚える(応用の型を作る)
考え方: すべての反応を丸暗記する必要はありません。代表的な“型”を身につけ、その亜種や条件の違いを比較する。
具体アクション: アルドール、Grignard、SN1/SN2、付加反応、脱離反応など“代表8〜10の型”をノートに一枚ずつ作成し、「いつ・どこで・なぜ起きるか」を短文でまとめる。これが“辞書”になります。sy.rikkyo.ac.jp
1週間のミニ学習プラン(例) — 手短に結果を出す
短期的に力を付けたい人向けの実例プラン(1週間)。
- 月〜火:代表反応2つの「電子の気持ち」を整理 → 手書きで反応機構を3回ずつ書く。
- 水:高校化学の弱点(酸塩基、電子の分布)を30分で復習。
- 木:別の代表反応2つに取り組む(書いて説明する)。
- 金:これまでの反応を組み合わせた問題(過去問や演習)を解く。
- 土:友人や講師に「この反応の流れを1分で説明」してフィードバックをもらう。
- 日:軽く復習+翌週の予定を逆算して計画作成。
(※短時間で回すのがポイント。忙しい時でも「書く→説明する」を最優先に。)
どうしてこのやり方が効くの?(エビデンス的な裏付け)
- 教育の方向性(薬学教育の目標):薬学教育のコアカリキュラムでも、薬学系では基礎知識の理解とそれを臨床応用につなげる力が求められると明記されています(薬学教育モデル・コア・カリキュラム)。有機化学の「機構理解」はその基盤です。厚生労働省
- 学習科学の示唆:単なる読み込みよりも「書く」「説明する」「問題で使う」といった能動的学習(アクティブラーニング)が深い理解を促します。化学教育でも、手を動かすワークや構造化された演習が効果を上げるという報告があります。azaleaenglish.com
- 大学の教材・講義実例:国内の有機化学講義ノートやOCWでも、巻き矢印の反復・演習を重視したカリキュラムが紹介されています。実際の講義で用いられている手法を日常学習に取り入れることが有効です。sy.rikkyo.ac.jp
よくある質問(Q&A)
- 反応を全部覚えたい気持ちが強い。丸暗記はダメ?
-
初期段階でいくつか重要反応を丸暗記するのは構いません。ただし「型」と「電子の動き」を理解することが最優先です。丸暗記だけだと応用問題で詰みます。
- 独学でこの学習法はできる?
-
できます。ただし「自分の説明を客観的に評価してくれる相手」がいると上達が早いです。友人と教え合ったり、授業外でTAや家庭教師に確認してもらうと安心です。sy.rikkyo.ac.jp
ちょっと本音(迷ったらどうするか)
短期間で結果を出したければ、「書く→説明する→問題で使う」のサイクルを回すのが最短です。独学がつらければ、大学のチュータ、TA、あるいは薬学分野に精通した指導者(個別指導・家庭教師)に「ここをどう説明する?」と投げて、フィードバックをもらってください。フィードバックがあるだけで理解のスピードは大きく変わります。厚生労働省
参考リンク(本文中で参照した公式/教育資料)
- 薬学教育モデル・コア・カリキュラム(厚生労働省) — 薬学教育の到達目標や学習の方向性が示されています。厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001198015.pdf - 大学の有機化学講義ノート(例:○○大学 有機化学講義資料) — 巻き矢印と反応機構の写し方、代表反応の整理が学べます。sy.rikkyo.ac.jp
(講義ノートの例ページ) - 化学教育・アクティブラーニングに関する教育実践報告(J-STAGE等) — 手を動かす演習の導入が理解を助ける事例。azaleaenglish.com
最後に(あなたへ)
有機化学は「慣れ」と「考え方」が合わされば、必ず得意科目になります。まずは1週間でできる小さな約束(毎日10分でも手で反応機構を書く)から始めてみてください。続けるうちに、反応が「暗記」ではなく「物語」として見えてきます。
もっと個別に相談したい場合は、授業ノートのチェックや具体的な反応の説明の仕方を一緒に確認できる指導者(TA・家庭教師)を探すのが近道です。必要なら、あなたの使っている教科書やノートを元に、次の学習ステップを一緒に作りますよ。