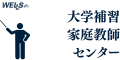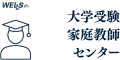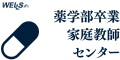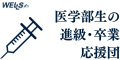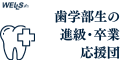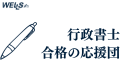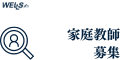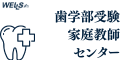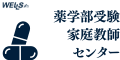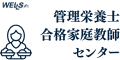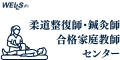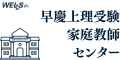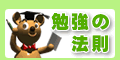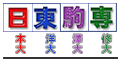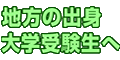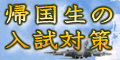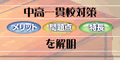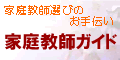薬学部の定期試験を乗り切る!留年を回避するための戦略的勉強法
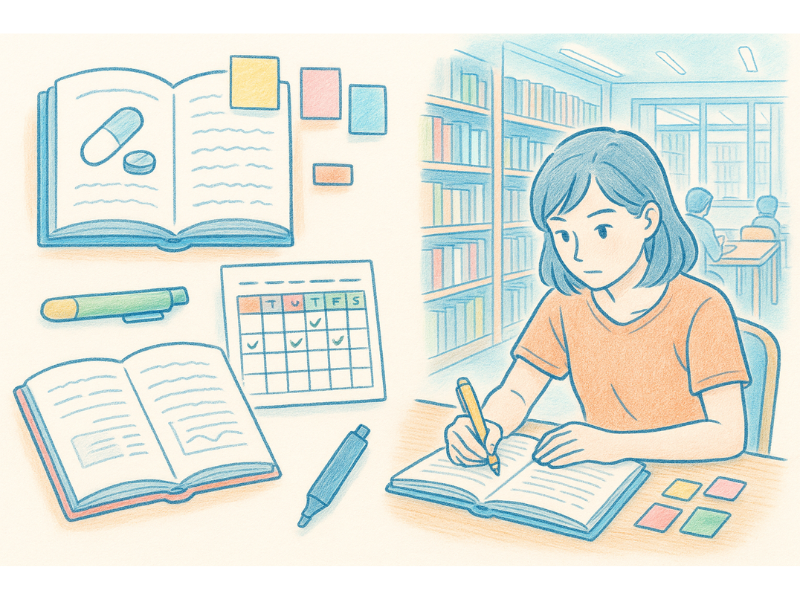
この記事では、薬学部の定期試験を計画的に乗り切り、留年リスクを下げるための具体的な勉強法とスケジュールの立て方をわかりやすく説明します。科目ごとの優先順位付け、過去問の使い方、短期〜中期の学習ルーチンを実例つきで示します。
なぜ薬学部の定期試験は難しいのか
薬学部の試験が難しい主な理由は次の通りです。
- 圧倒的な暗記量(薬名・作用機序・副作用など)
- 基礎→専門の積み上げ構造(低学年の理解不足が後に響く)
- 応用力が問われる出題(症例統合問題や計算問題)
これらを踏まえて、早めの計画と「アウトプット中心」の学習が鍵になります。
試験1ヶ月前からの必勝スケジュール(4段階)
| 期間 | やること(優先度) |
|---|---|
| 試験1ヶ月前 | シラバス・過去問分析。科目ごとの出題傾向と重要度を把握し、大まかな時間配分を決める。 |
| 試験3週間前 | 教科書・ノートをざっと通読して全体像を把握(細部は追わない)。 |
| 試験2週間前 | 頻出事項の暗記と理解を本格化。授業で強調された箇所を重点的に。 |
| 試験1週間前 | 過去問・問題集でアウトプット。誤答は原因分類して即復習。模擬時間で時間配分を確認。 |
科目別の勉強法(暗記系 vs 理解・計算系)
- 暗記系(薬理学・生化学など)
- アウトプット重視:短問→解説→間隔復習(1→3→7日)
- 語呂ではなく「意味」をセットで記憶(例:作用機序+臨床意義)
- 理解・計算系(物理化学・薬剤学など)
- 公式の意味を言語化してから練習問題へ
- 単位チェックを必ず行う習慣をつける
過去問の使い方(最小限で最大効果)
- まず「過去出題テーマ一覧」を作る(3〜5年分)。
- 年ごとに解いて「出題パターン」と自分の弱点を把握する。
- 間違えた問題は「原因分類」する(暗記不足/理解不足/ケアレス/時間配分)。
- 同じテーマを別角度で3回解いて定着させる。
過去問は「答えを覚える場」ではなく「クセ(出題の狙い)を読む場」です。
一日の学習モデル(例:試験2週間前)
- 08:30–10:00:理解系(集中力の高い午前に) — 公式確認+例題3問
- 10:15–11:00:短問復習(暗記系の確認) — フラッシュカード 30分
- 13:00–15:00:過去問演習(本番形式で) — 時間計測で解く
- 15:15–16:00:誤答レビュー(原因分類→教科書確認)
- 20:00–20:30:軽い復習(当日まとめ)
よくある失敗と即効改善策
- 一夜漬けで誤魔化す → 日割りで小さな目標を作る。
- 過去問を流し読みする → 実際に解いて「なぜ」を掘る。
- 単位・桁で落とす → 問題を解くたびに単位を声に出して確認する習慣。
- 時間配分を誤る → 模擬試験で必ず時間管理を練習する。
試験直前のチェックリスト(コピー可)
- 過去問3年分を一巡した(間違いは分類済み)
- 重要公式は1枚にまとめてある(言葉で説明できる)
- 計算問題で単位チェックの癖がついている
- 当日の持ち物(筆記具・計算機・学生証)を前日夜に準備
- 睡眠時間を確保(6時間以上推奨)
メンタル管理と体調
学習効率は体調に強く依存します。短期追い込みでも次を守ってください:睡眠、栄養、短い運動。追い込み期ほどセルフケアは重要です。
参考文献
- PASS MED.(2023) 薬学部の進級・定期試験対策:過去問題を暗記して徹底活用. https://passmed.co.jp/pharmacy/archives/145
- メディカルウィング HOPE(2024) 薬学部の定期試験を乗り切るポイント. https://medhicalwinghope.com/help-info/article/薬学部の定期試験を乗り切るポイントを徹底解説/