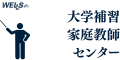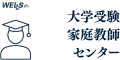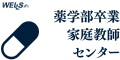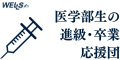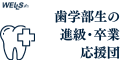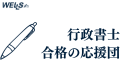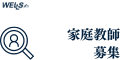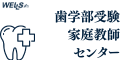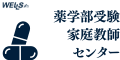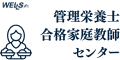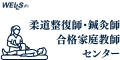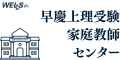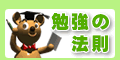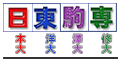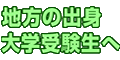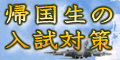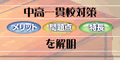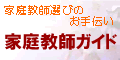薬学部「薬事法規」を完全攻略!国試で点を稼ぐ戦略的勉強法

この記事では、薬剤師の業務を支える主要な法規と、その学習方法を国家試験で得点につなげる形でわかりやすく整理します。条文の丸暗記にとどまらず「法律の目的」と「現場でどう適用するか」を結び付けて学ぶことで、実践力と得点力が同時に伸びます。
はじめに
- 法規は「目的」と「構造」を理解すると覚えやすくなります。
- 優先順位をつけて主要法令(医薬品医療機器等法、薬剤師法、麻薬法、保険関係法など)を押さえます。
- 過去問演習で「実際の場面でどう判断するか」を反復し、条文と結びつけて説明できるレベルを目指します。
なぜ薬事法規は「ただの暗記」では通用しないのか
- 目的理解が不可欠:条文は背景となる「目的」が分かると意味が取れやすくなります。
- 応用力が問われる:国家試験では「この場面で薬剤師はどうするか」を問う設問が増えています。条文を事例に適用する力が必要です。
学習の3段階アプローチ(効率的に進める流れ)
ステップ1:全体像を把握する(学習初期)
- 教科書や公式資料で主要制度の体系をざっと把握します(どの法律が何をカバーするか)。
- まずは範囲の「地図」を作るイメージで、細部は後回しにします。
ステップ2:重要法規の重点学習(学習中期)
以下の法令は最優先で詳細を学んでください(目的・主要規定・代表的な条文の扱い方を押さえる)。
- 医薬品医療機器等法(医薬品の製造・販売・安全対策等)
- 薬剤師法(資格・業務・義務)
- 麻薬及び向精神薬取締法(管理・処方の厳格化)
- 健康保険関係法(保険調剤の仕組み)
学ぶ際は「目的→主要条項→現場での適用例」の順で整理すると理解が深まります。
ステップ3:過去問演習で運用力を磨く(学習後期)
- 過去問は「正解を選ぶ」だけで終わらせないでください。必ず「なぜそれが正しいか/他はなぜ違うか」を条文や制度の観点で説明します。
- 事例問題や処方例を使って、条文の適用を頭の中でシミュレーションする訓練を繰り返します。
実務寄りの学習テクニック(すぐ使える)
- 条文→目的を一行で要約:条文を読んだら「この条文は何を守りたいか」を一文にする。
- 事例で覚える:処方ミス、麻薬管理、保険上の取り扱いなど具体例と条文をセットで学ぶ。
- 頻出ワードの定義を整理:販売業・製造業・輸入差・保険請求の各用語の意味を明確にする。
- 判例や通知の要点把握:重要な通知(局長通知など)は指定箇所だけ押さえ、実務での影響を理解する。
優先的に押さえるべき出題ポイント(国家試験)
- 医薬品の販売管理・製造責任の所在(誰が何を守るか)
- 薬剤師の義務(情報提供、調剤の範囲、守秘義務など)
- 麻薬・向精神薬の管理・処方に関する規制
- 保険調剤の基本ルール(処方箋の扱い、診療報酬・保険請求の基礎)
- 医薬品安全対策(副作用報告、回収の流れ)
よくある学習の落とし穴と対処法
- 落とし穴:条文だけ覚えて事例対応ができない → 対処:過去問・事例を通じて「条文の使い方」を身につける。
- 落とし穴:条文が多すぎて手が回らない → 対処:主要法令の「目的」と「代表的な規制(出題対象)」に絞る。
- 落とし穴:通知や通達の扱いを軽視する → 対処:重要な局長通知や省令の要点は要約カードを作る。
今日からできる具体アクション(3つ)
- 代表的な法令を1つ選び、目的を一文で書く。
- 過去問を1題解き、「なぜその解答か」を条文ベースで1〜2行説明する。
- 麻薬や保険関係など、実務上の注意点が多い分野は事例を1つ調べて要点をまとめる。
参考リンク(名前とURL)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134596.html
- e-Gov 法令検索(法令本文の検索): https://elaws.e-gov.go.jp/
- 薬剤師国家試験 出題基準(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/H28kizyun.pdf
- e-REC(過去問解説など参考サイト): https://e-rec123.jp/
- PMDA 添付文書等情報検索(医薬品情報の一次情報): https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/