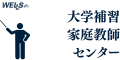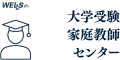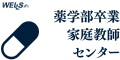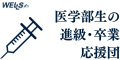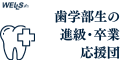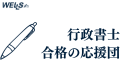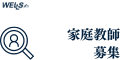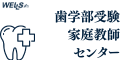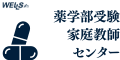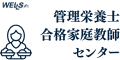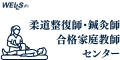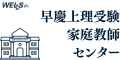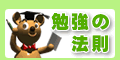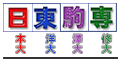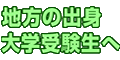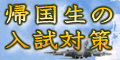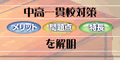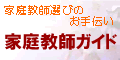薬学部からの進級を確実にする実践ガイド
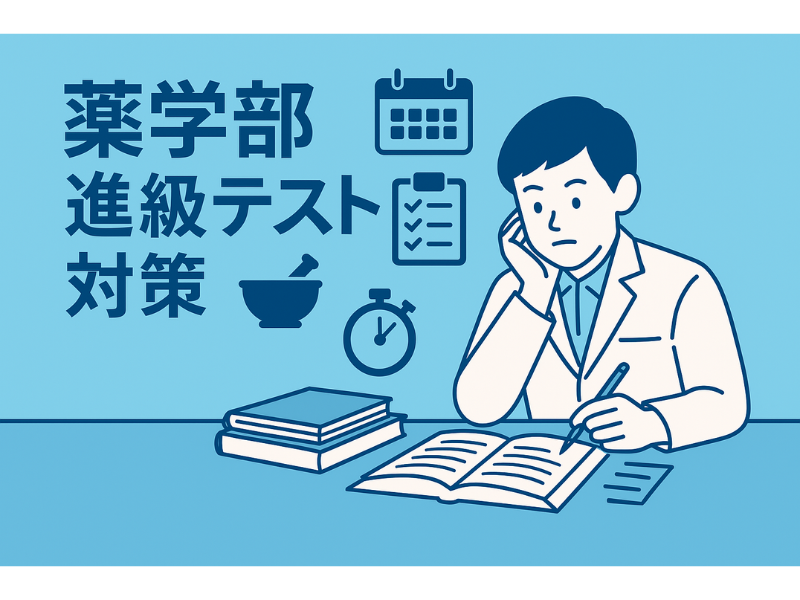
結論:
今学期の進級を確実にするには、まず「絶対に落とせない科目」を最優先にし、出題傾向に合わせた本番想定演習(到達度チェック)+想起(取り出す)練習の反復を短期で回すことが最も効果的です。必要に応じて、短期集中の個別支援を戦略的に使う判断をしてください。文部科学省+1
なぜこの方法が効くのか
- 薬学部の進級・修学状況については、文部科学省の調査が示すように学年ごとの進級率に差があり、早期の対応が修学状況改善に寄与することが指摘されています。進級リスクが高い場合は速やかな対策が重要です。文部科学省
- CBT(臨床実務に進むための共用試験)は、実務実習参加の要件に深く関係しており、基礎の穴を放置すると後の実習進行に影響します(CBTの目的と構成の公的説明)。PhCAT
- 学習科学のレビューでは、想起(retrieval practice)と分散(spaced)学習が記憶と応用力の定着に強い効果を持つと示されています。したがって「問題を解いて取り出す」運用が短期での定着に最適です。Google Sites+1
- 教育研究・メタ分析では、個別化・少人数介入(適切に設計された個別指導)は学習成果を改善する傾向が示されています。短期で点数が必要な局面では、外部支援を戦略的に使う合理性があります。リサーチマップ+1
今すぐやるべき【5つの優先行動】
- 進級ルールを正しく確認する
- 大学のシラバス/学務の進級基準(必修・単位数・CBT受験資格)をまず確認し、何が「絶対に落とせない」かを明確にする。文部科学省
- A/B/Cリストをつくる(48時間で)
- A:今学期中に合格しないと進級が危ない科目(最優先)
- B:できれば合格したい科目(再試等で調整可)
- C:優先度低
- 48時間以内にA科目の「合格ライン(点数・出題形式)」と「合格するための最短行動」を書き出します。文部科学省
- 本番想定演習(到達度チェック)を回す
- 過去問や授業の確認問題を「本番と同じ時間と形式」で解き、合格ラインを超えられるか確認。出た誤答は想起練習(見ずに説明・空で解く)で即修正。学習科学で有効性が示されているやり方です。Google Sites+1
- 短期集中プラン(Day0–Day14の例)
- Day0:進級ルール確認+A/B/C作成。
- Day1–7:A科目集中(毎日「本番想定演習」+誤答ノート→想起で潰す)。
- Day8–14:Aの仕上げ→Bの穴埋め。進捗は数値(問題数・正答数)で管理。PhCAT
- 学内支援を最大限に利用し、足りない分を外部で補う
- まず教務・補講・チューターを活用(無料で即効性あり)。学内で補えない「基礎の抜け」は短期個別指導で効率的に埋める判断が合理的です(個別介入の効果にエビデンスあり)。神戸大学附属図書館+1
72時間ルール
- Day0(今日):進級基準を確認 → A/B/C作成 → A科目の過去問1回を本番想定で解く。文部科学省
- Day1–2:A科目を毎日2時間、本番想定演習+誤答ノート作成。教員へ質問(オフィスアワー)を予約。Tetsuya’s マインドパレス
- Day3:A科目の想起テスト(見ずに説明できるか)で検証。改善箇所を具体的にする。note(ノート)
2週間(Day1–14)テンプレ(実行しやすく)
- Week1:Aに集中(演習80%/振り返り20%)。毎日「解いた問数/正答数」を記録。
- Week2:A仕上げ→Bを短時間で穴埋め。到達度チェックで合格水準に達しない場合は短期個別を検討。リサーチマップ
学習の「やり方」── 科学的に効くテクニック(すぐ使える)
- 想起(取り出す)練習を優先:読むより「見ないで解く/説明する」を繰り返す。記憶と応用力の定着に効果的です。Google Sites
- 分散学習:詰め込みより、日にちを分けて何度も短時間で復習する方が定着します。Google Sites
- 過去問中心で出題傾向を把握:短期で確実に点を作るには最も効率的です。PhCAT
- 数値化して管理:毎日「解いた問題数/正答数」をつけて小さな勝ちを見える化。継続につながります。
個別支援(家庭教師)を入れるとしたら
- 入れるタイミング:A科目の到達度チェックで合格水準に達しないと判明したときが判断ライン。時間が限られている局面では、設計力で点を作る判断が合理的です。リサーチマップ
- 選び方のポイント:講師が大学の出題傾向を理解しているか、手持ち教材を繰り返す指導方針かを確認しましょう(教材を増やさず“深掘り”する方が定着しやすいという研究的示唆があります)。神戸大学附属図書館+1
よくある不安にやさしく回答
- 「時間がない」 → だからこそA/B/Cで切り分け、Aだけは絶対に守る。それで進級確率は大きく上がります。文部科学省
- 「一人で無理かも」 → 大学の補講・チューターをまず使い、小さな成功を積む。足りない部分を短期で補う判断は合理的です。Tetsuya’s マインドパレス+1
参考(本文の主な根拠)
- 文部科学省「薬学部における修学状況等」調査(進級・修学の公式データ)。文部科学省
- 薬学共用試験センター(PhCAT)「CBTの概要」 — CBTの目的・出題方式・大学での位置づけ。PhCAT
- JSET SIG-ID 等による「想起」と「分散学習」のレビュー(学習科学の日本語レビュー)。Google Sites+1
- John Hattie らの可視化された学習・教育効果のレビュー/国内の教育メタ分析(個別化指導の効果に関する総合的知見)。リサーチマップ
- 学外指導(塾・家庭教師)に関する国内研究(効果の傾向を示す論考・事例)。神戸大学附属図書館