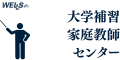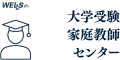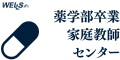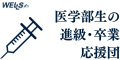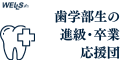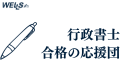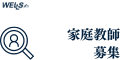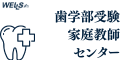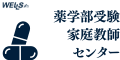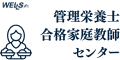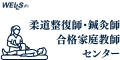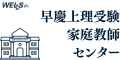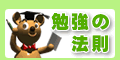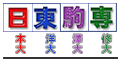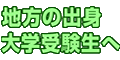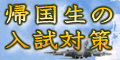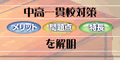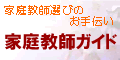薬学部3年の今が分かれ道:CBT/OSCEへ向けた最短トリアージで留年リスクを下げる
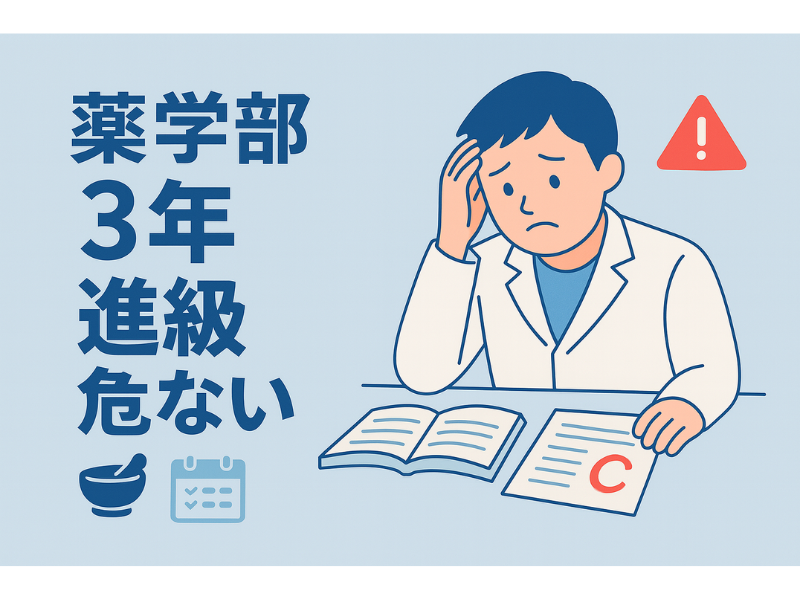
結論:
3年生の今、CBT(知識評価)に向けた準備を始めなければ、結果的に5年次の実務実習参加や進級に影響が出るリスクが高まります。逆に、3年段階で要点を絞ってCBT対策を進めれば、そのリスクは大きく下がります。OSCE(技能評価)は重要ですが、まずはCBTの土台固めを優先してください。
CBTの位置づけと重要性(やさしく・簡潔に)
CBTは薬学教育における知識の到達度を評価する共用試験で、多くの大学で4年次の冬に実施され、実務実習(5年次)へ進む際の判断材料となります。範囲は広く、1〜3年で学ぶ基礎知識が土台になりますので、「3年のうちに基礎の穴を埋める」ことが合格可能性に直結します。
- PhCAT(薬学共用試験センター)公式(試験の目的・CBT概要):https://www.phcat.or.jp/ 。
- PhCAT CBT ページ(出題範囲・サンプル等):https://www.phcat.or.jp/cbt/ 。
なぜ3年でCBT準備を始めるべきなのか(論理的に・わかりやすく)
- 出題の土台が3年までの学習にある — 基礎が不十分だと、4年での短期集中では補えないことがある。
- 大学の進級運用と連動している場合が多い — 学年ごとの単位要件や受験資格が設けられていることがあり、3年での遅れが後のスケジュールを圧迫することがある。
- 対策は量より“質×頻度”が効く — 幅広い範囲をただ詰め込むのではなく、頻出領域に絞った反復演習と模擬形式の訓練で得点効率を上げるのが現実的で有効です。
(参照:PhCAT 試験概要/各大学の共用試験案内)
実務的なCBT対策
CBTは「範囲が広い」ことが最大の難所です。以下を小さく、確実に進めてください。
- 必ずやること(今日から)
- 履修要項・シラバスで必修&CBT頻出科目を確認する。
- 優先順位の付け方(シンプル)
- A:必修かつ配点が高い科目(最優先)
- B:CBTで頻出する範囲(短期で得点化しやすい)
- C:残り(合格ラインで割り切る)
- 演習のやり方(得点効率を上げる)
- 過去問・模擬問題を「時間を計って」解く(実戦慣れ)。PhCATのサンプル問題も活用。
- 頻出テーマを3〜5に絞り、そこを確実にする(ノート化→反復)。
- 計算・処方・薬剤知識は「問題を解く」ことで定着するため、問題演習中心に回す。
- 時間管理
- 模擬形式で時間配分を体に染み込ませる(CBTは時間内に解き切る練習が重要)。
OSCEはどう位置づけるか
OSCEは技能・態度の評価で重要ですが、CBTが合否の土台を決める性格が強い場面もあります。OSCE対策は並行して進めるべきですが、まずはCBTの基礎固めを優先し、余力で構造化された模擬(チェックリスト+録画フィードバック)を行ってください。
続けるための現実的なコツ(やさしい口調で)
- 満点を狙わなくて大丈夫。 まずは合格ラインを固めましょう。
- 毎日短時間の反復(30〜90分)を続けることが大切です。
- 模擬は記録して振り返る:できれば時間を計って解き、間違いの傾向を週ごとにまとめて直してください。
締め(短く穏やかに)
3年生のうちにCBTの基礎を固めることは、5年次の実務実習にスムーズに進むための最善策です。無理なく、今日の「小さな一歩」から始めてみてください。
参考リンク(日本語・一次情報)
- PhCAT(薬学共用試験センター)公式: https://www.phcat.or.jp/ (試験の目的・運用)。
- PhCAT FAQ(CBTの実施時期ほか): https://www.phcat.or.jp/exam/faq/ 。
- PhCAT CBT ページ(出題例・対策の指針): https://www.phcat.or.jp/cbt/ 。
- PhCAT 試験概要(CBT/OSCEの趣旨): https://www.phcat.or.jp/exam/about/ 。
- 京都大学 薬学部:共用試験案内(大学側の運用例): https://www.pharm.kyoto-u.ac.jp/education/undergraduate-education/pharmacy-education/common-test/ 。
- 北海道大学 薬学部:実務実習スケジュール例: https://www.pharm.hokudai.ac.jp/practice/schedule.html 。