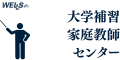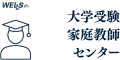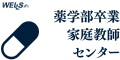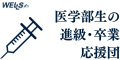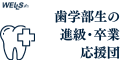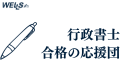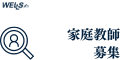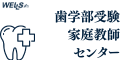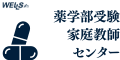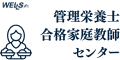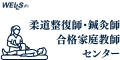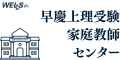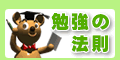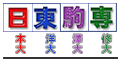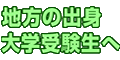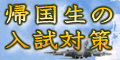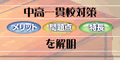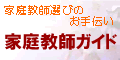薬学部の膨大な学習量を制覇する「逆算思考」学習計画術

結論:
最終ゴールを具体化してそこから逆算するだけで、やることが明確になります。
週次で見直し・記録を行えば、計画倒れは防げます。
はじめに — こんな悩み、ありませんか?
「試験前はいつも一夜漬け」「計画は立てるけど続かない」「何を優先すれば良いかわからない」——薬学部の学習は量も質も大変で、これらの悩みは極めて一般的です。ここでは、日本の教育機関の知見を踏まえつつ、今日から使える逆算思考の4ステップを説明します。
なぜ計画が続かないのか?(エビデンスに基づく簡単な説明)
日本の教育関連機関の示すところでは、学生が計画を続けられない主な理由は次の3点です。
- 目標が遠く・抽象的である:最終ゴールだけだと、日々の行動につながりにくい(文部科学省の学習支援方針参照)。
→ 文部科学省:学習支援の考え方(https://www.mext.go.jp/) - 優先順位が不明瞭:やることをただ並べるだけで重要な学習が埋もれる傾向がある(学生の学習実態に関する報告)。
→ Benesse 教育研究所(学習実態データ):https://berd.benesse.jp/ - 進捗が見えないため挫折する:記録・可視化がないと努力の手ごたえが得にくい(学生支援の推奨事項)。
→ 日本学生支援機構(JASSO):https://www.jasso.go.jp/
これらを踏まえ、逆算で「具体的に」「可視化して」「定期的に見直す」ことが効果的です。
逆算式・学習計画の 4ステップ(やさしく・具体的に)
ステップ1:ゴールと現状をはっきりさせる(When / What / Where)
- 例:「8月31日の有機化学定期で80点以上」のように、日付・科目・到達レベルを明記。
- 現状は模試や過去の点数で数値化しておく(例:章ごとの正答率、模試の分野別スコア)。
理由:具体的なゴールは日々の行動を導きます(文科省の指針にも合致)。
ステップ2:やるべきタスクを全部洗い出す
- 教科書の章、問題集の周回回数、過去問の年数、暗記項目リストなど、思いつく限り列挙。
- この段階で順序や時間は気にしない。「まずはすべて書き出す」のがコツ。
ステップ3:優先順位をつけ、所要時間を現実的に見積もる
- 各タスクを「試験で出る確率(重要度)」×「必要時間」で評価。
- 大事なのは現実的な時間見積もり。見積もりはやや余裕を持たせると継続しやすいです。
ステップ4:カレンダーに落とし込む(逆算して日程化)
- ゴール日から逆にスケジュールを組む(長期→中期→短期)。
- 例:「試験1週間前に問題集3周を完了」→「今週は2周目を完了」→「今日はこの章を終える」
- 週に一度(30分程度)見直す時間を必ず確保すること。
実行を成功させる“今すぐ使える”コツ(日本の現場指針に基づく)
- スモールゴールをつくる:小さな達成が継続の原動力になります(JASSO 推奨)。
- 学習の見える化:勉強時間や演習数を記録すると自己効力感が上がる(Benesse の示唆)。
- バッファ日を入れる:予定通りに進まないことを前提に余裕日を作る。
- インプット→アウトプット→白紙再現のサイクルを回す:理解→定着→再現の順で学ぶと効率的です。
- 週次の振り返り(リライト):計画は固定しない。週に一度、進捗に合わせて最適化しましょう(文部科学省の学習支援方針)。
よくある間違いとその直し方(短く)
- 完璧主義で遅れを許さない → 直し方:80%で前に進む習慣をつける。
- 時間だけ重視して質が伴わない → 直し方:何をどう解くか明確にする(目的をセット)。
- 計画を作ったら見直さない → 直し方:週1回は必ずリセット。
まとめ(行動チェックリスト)
- 今日:まず1つ、明確な小ゴール(例:今週で問題集10ページ)を決める。
- 明日:ゴールから逆算して今週のタスクを書き出す。
- 毎週:見直し(30分)を実行する。
この3つを続けるだけで、計画倒れはかなり減ります。
参考リンク(本文で参照した日本の公的・教育機関ソース)
- 文部科学省(MEXT) — 大学教育・学習支援: https://www.mext.go.jp/
- 日本学生支援機構(JASSO) — 学生支援・学習法ガイド: https://www.jasso.go.jp/
- Benesse 教育研究所(BERD) — 大学生の学習実態: https://berd.benesse.jp/
- 国立教育政策研究所(NIER) — 教育研究・学びの科学: https://www.nier.go.jp/
さいごに
個別で計画作成や進捗管理が苦手なら、薬学部専門の家庭教師(月4回・週1回・1回120分)が伴走して計画を作り、週次で調整・管理します。自力での実行が難しい方には有効な選択肢です(サービス利用は任意です)。