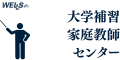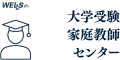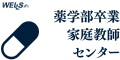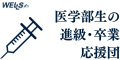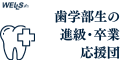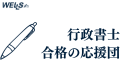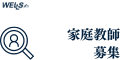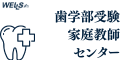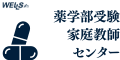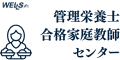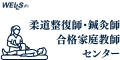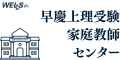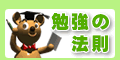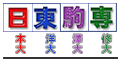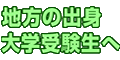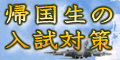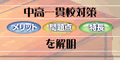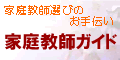薬学部「衛生薬学」の攻略法|暗記とデータ解析を制する勉強法

この記事では、衛生薬学の学習を効率的に進め、国家試験で確実に得点するための実践的な学習法をわかりやすく整理します。範囲は広いものの、出題は比較的定型的です。過去問を軸に学び、図表の読み取り力を鍛えれば、着実に点数につながります。
衛生薬学とは(学ぶべき領域の概観)
衛生薬学は、環境・食品・職場・感染症など、公衆衛生に関わる広い領域と医薬品の関係を扱います。主に次の分野が含まれます。
- 環境衛生:大気汚染・水質汚濁・化学物質による健康影響
- 食品衛生:食中毒の原因微生物・添加物・栄養学
- 労働衛生:職場の有害因子と健康障害
- 疫学・統計:疫学調査の読み取り、リスクの評価
これらは薬剤師が地域保健や薬の安全情報を扱う際に必要となる基礎知識です。
衛生薬学が得点につながる理由
衛生薬学は範囲が広い反面、国家試験では型の決まった問題が多く出題されます。すなわち、適切に優先順位をつけて学べば、効率よく得点を伸ばせる科目です。また、図表やグラフの読み取り問題が増えており、知識に加えてデータ解析力が求められます。
効率的な学習法(3つの基本)
- 過去問を学習の中心に置く
直近7年分程度の過去問を繰り返し解くことで、出題形式と頻出項目を把握します。間違えた問題は「なぜ正しくないか」まで説明できるようにし、出題パターンを体に馴染ませます。 - 知識を関連付けて覚える
単独の用語を丸暗記するのではなく、関連情報をセットで整理します。たとえば「食中毒」なら原因菌・潜伏期間・代表的症状・原因食品・適切な対応(加熱や保存方法)を一緒に記憶します。 - 図表・データの読み取りに慣れる
疫学の基礎(相関と因果の違い、リスク比やオッズ比の意味)や、グラフの軸・単位を正確に読む練習を日常的に行います。過去問や報告書の図表を題材に、何が示されているかを短く要約する習慣を付けましょう。
具体的な勉強の進め方(実行しやすい手順)
- 過去問を1セット(年度分)通して解く。正答率が低い分野に印をつける。
- 印をつけた分野を、教科書の該当箇所で「関連事項」をセットで確認する。
- 図表問題は「問題→図の読み取り→自分の言葉で要点1〜2行」に要約する。
- 週に1回、過去に間違えた問題だけを短時間で復習する(間隔復習)。
これを繰り返すことで「覚えるべき箇所」と「図表の読み方」が自然と身につきます。
データ解析問題の押さえどころ(最低限)
- グラフの縦軸・横軸と単位を必ず確認する。
- 相関がある=因果関係ではないことを常に念頭に置く。
- リスク比(relative risk)とオッズ比(odds ratio)の概念を簡潔に整理しておく。
- 有意差に関する表記(p値など)の基本的な意味を押さえる。
(専門的な数式までは不要ですが、「何を読み取るべきか」を判断できることが重要です。)
よく出るテーマ(頻出分野)
- 食中毒(原因微生物、潜伏期間、予防法)
- 食品添加物と安全基準(基準値の意味)
- 感染症の流行パターンと簡単な疫学指標
- 環境有害物質(例:PCB、ダイオキシン等)の健康影響と関連法規
- 労働衛生の基礎(作業環境測定、職業病の概要)
これらは出題頻度が高いため、優先的に押さえておくと得点効率が良くなります。
つまずきやすい点とその対処法
- 暗記が苦手:関連情報(原因・症状・対応)をセットで覚えると忘れにくい。
- 図表が読めない:図を見て「まず何を読むか(軸・単位・凡例)」をチェックする短い手順を習慣化する。
- 法規がややこしい:重要な条文や基準値は「何を守るためのものか」を一文でまとめる。
まとめ(今日からできるアクション)
- 直近の過去問から「今日1題」を選んで解く。解答だけで終わらせず、誤答の理由と図表の読み取りポイントを1〜2行でメモする。
- 食中毒や環境有害物質など、頻出テーマを3〜5項目に絞って関連情報を整理する。
この方法を継続すれば、衛生薬学は確実に得点源になります。
参考リンク(名前とURL)
- ファルマスタッフ 国試対策コラム(衛生薬学の勉強法):https://www.38-8931.com/pharma-labo/yakugaku_topics/article/kokushicolumn_04.php
- 薬剤師国家試験 出題基準(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/H28kizyun.pdf
- PMDA 添付文書等情報検索(医薬品情報の一次情報):https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/
- e-REC(過去問解説等):https://e-rec123.jp/